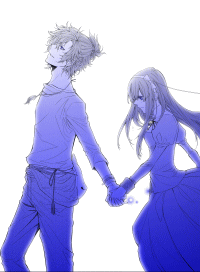 |
|
| さよならのために
|
|
「――――」 ごめんなさい、と。 そう呟いた自分を自覚した瞬間に覚醒した。 瞬かせた瞳には灰色の景色がまず映る。けれど元々はアイボリーの壁紙が敷き詰められていたのだろう。視界に映る剥き出しの無骨なセメント材に、そんな名残を僅かに見い出し、もはや何を驚くこともなくそこがどこだか思い出して撫子はゆっくりと首を巡らした。とはいってもそれはすこし傾けただけですぐに行き場を失くし、止まってしまったのだが。 (つめたい) ベッドのシーツに頬を押し付ければ、それまで外気にさらされていた部分がひんやりとしたその冷たさを伝えてくる。 目蓋を下ろし、再びそっと目を閉じた。そうすることで今しがた見たばかりの夢が少しでも和らぐように。 (……トラ) しかし呟いた、その名が撫子の胸の内で痛みをもたらさない日はない。きっと永遠にこの痛みは自分を縛り付けてゆくのだろう。それをもう撫子は諦観の念とともに覚悟していた。 何故ならそれは忘れもしない2010年、秋のこと。 時の停滞という脅威の事象を経て、突然精神だけを十年後の九楼撫子へと転生させられた自分は、そこでそう遠くない未来において、交通事故に遭う運命を教えられた。それから十年もの間、【事故にあった九楼撫子】は一度も目覚めることのない深い眠りに落ち、そしてその目覚めることのなかった二十二歳の撫子の身体のなかで十二歳の撫子は目を覚ますこととなったのだ。夢のような話だが、自分の目の前には二十二歳の……もはや別人とも言えるくらいに成長した幼馴染み――加納理一郎がいた。 他にも西園寺寅之助、時田終夜の二人もいた。 この二人も理一郎同様共に成長した十年後の姿をしており、目覚めた撫子をひどく驚かせた。そして三人の内、西園寺寅之助……トラだけは撫子のことをひどく他人行儀な冷めた眼差しで、あんたなんか知らないと切り捨てるように言い放った。 一ヶ月。毎日ではなかったものの、確かに共に過ごした時間を持つ撫子にとっては、トラのその眼差しはとても辛く、堪えるものだった。 撫子は憶えている。何一つ自分と共有する記憶を持たないかつての友であっても。 そのわかりづらい、不器用なやさしさを。 そうした重ならない思いは気付けばいつもすれ違い、その度に撫子のことを傷付けた。 けれどこうやって沢山、撫子の知らない……まだまだ多くの人たちが元の世界とは別の、全く違う人生を歩むことになったのだ。 目覚めて初めて知ったその世界は、右も左もわからぬ撫子にとって多くの枷と柵を強制的に促したが、濁った雲に覆われた暗い空の下――望むべくもない一方的な別れを強いられたことへの憤りは決して無くなるものではなかったが――明けることのない絶望に彩られたその世界からも同時に目を背けることもできなくなってしまった。 壊れた世界で、壊れた時間を刻み続ける……そんな世界がとても哀しく、そして、 (……トラ) 撫子の脳裏に十二歳のトラと二十二歳のトラ、そのどちらともの顔が浮かんで、思い出せば胸が押し潰れるように痛んで。 違うところはたくさんあった。けれど同じぐらい重なり合う部分も多かったふたりのトラ。十二歳のトラに恋を自覚したことはない。けれどこの世界で時間を過ごすうちに、気付けば自分はこの壊れた世界のトラを好きになっていた。 もしも同じように元の世界で何事もなく共に時間を過ごしていたなら、或いはもしかしたら元の世界でも自分は「西園寺寅之助」という人間に恋をしていたかもしれない。 すべては仮定である。けれどそうやってこれからもそのそばでくだらない話をしたり、笑いあって、たまに衝突をしながらも共に同じ時間を過ごしていきたい、と思うくらいには。 (……好きだった) そんなふうに大事に想っていた。そんな十二歳のトラを、自分の好きな――二十二歳のトラは手にかけた。殺したのだとはっきり明言されたわけではない。トラは何も言わなかった。 だが零れ落ちた一本のナイフ。幼い十二歳の彼がその眼にいつも付けていた黒い眼帯。血に濡れたそれらと「【オレ】以外の寅之助はもういらないよな」と確認するよう問いかけてきた二十二歳のトラの発言を思えば……こわい考えを止めることができない。 撫子が見せた一瞬の迷い。躊躇いのせいで。 (トラはトラを) たとえ違う世界。違う自分だったとしても。 自らの手で自らを殺してしまったかもしれないのだ。撫子が迷った、そのせいで。或いはもしかしたら、それをトラは自分に知らしめたかったのかもしれない。 (……わからないけど) ただすべてはもう過ぎたことで、終ったことで、どんなに声を嗄らし、泣いて悔やんでも、あの日の自分が――過ぎた時間が巻き戻ることはない。判断に迷った自分の躊躇いがふたりの人生を狂わせ、壊してしまった。 それを、忘れてはいない。 「ビショップと鉢合わせして、それで誰も連れていかれずに済んでるんだもの。幸運だったわ」 数多くいる政府の人間のなかで、撫子の知る限り、ビショップほど腕の立つ人間はいない。 そうしてこの組織の中で彼とまともにやり合えるのはトラくらいなもので、だからこそ今回偶然鉢合わせた際にトラがいて本当に良かったと思う。でなければ終夜を含めた他の仲間たちは、おそらくみな捕らえられていただろう。 (って言ってもみんな要領はいいから大丈夫かもしれないけど。というより、どちらかといえば……) そうね。と内心でじっくり吟味するよう頷いてから。 「うん? どうしたのだ、撫子?」 組織一、運動神経のない男と目されている終夜だけは、トラがいなければ完全にアウトだったかもしれないと、申し訳ないながらついそう素直に思ってしまった。 「……なにやら憐れみの目で見られているような気がするが……まあよい。私がみなに迷惑をかけたのは紛れもない事実だ。私があの場で転んだりせねば、寅之助も巻き添えを食わずに済んだのだ。済まぬ、撫子。そなたらの大事な約束を破らせ、寅之助をこのように傷付けてしまったのは私だ。煮るなり焼くなりそなたの好きにせよ」 覚悟はできている、と。 無駄に悲愴な眼で訴えかけられ、「あ、あのね……終夜?」と、思わず撫子は頬を引き攣らせた。芝居がかった冗談のようなそれだが終夜は本気で言っている。何がそう彼を駆り立てるのかはわからないが、たとえばここで切腹をと望めば、まず間違いなく本気でやろうとするだろう。 (……刃物持つ手すら危うそうだけど) そしてその前にまた転びそうだ。 その辺り、よく心得ている。 それゆえに。 苦笑いを浮かべながら、 「いいわよ、終夜。約束ならまたすればいいだけだもの」 できるだけ誤解を生まぬよう、やさしい声で言い諭す。 「だがしかし」 「――終夜」 何故こんな話を、こんなにも真剣にしているのだろうという疑問が湧くことには湧いたが、気にしたら負けだ。というよりもトラとの約束を知っている終夜のほうがよほど気になったのだが。 一先ず。 「怪我人がそんな変な気なんて回さなくていいの。そんなことより、大人しく治療されてくれたほうが、むしろよっぽどありがたいわ」 迷うことなくさっくりと。相手のペースを自分のほうへともってゆくことに専念する。でなければ彼と話などとても続かないし、先に進まない。 (わかってるもの) 共に過ごした――あの一ヶ月間のなかでそれを学んだ。わかってる。もう、そんなこと。それをそっと胸のなかで囁いて。 「だからね? 治療させて、終夜」 望むのはそれだけ。責めるものなど何もない。 微笑んで言うと、唯一同じ記憶を共有する終夜は、ぱちりと驚いたように瞳を瞬かせ、やがてゆっくりと春の陽だまりのような柔らかい笑みをそこに浮かべた。 「相変わらずそなたは潔い女子だな。時代劇で言うなら、辻斬りにあっても最後まで生き残り、奉行所に駆け込める女子だ」 「……ありがとう」 きっと、まあ……褒められているのだろう。 若干複雑な思いに囚われながら、瓦礫のなか、どうやら思いきり派手に転んだらしい終夜の腕を取る。深くはないが、見れば浅い切り傷擦り傷、打ち身のアザがあちこちに見て取れる。 受け身が取れなかったのはもはや一目瞭然の仕様だった。 (絆創膏……足りるかしら) しかしこの程度で本当によかったと息を吐きながら、 「トラ。ほら、あなたも」 「……こんぐれー大したことねーよ」 先程から妙に大人しいトラへと同じく声をかければ、言外に治療を拒否られた。その上、顔もみない。不機嫌なのを思えば返事をしてくれただけまだマシなのだろうが。 それでも。 「大したことないって……」 またも怪我を軽んじる発言に撫子は憮然とする。大小、程度の差はあっても怪我をしていることに変わりはないのに。 「……昨日の怪我だってあるでしょう? 絆創膏とか目立って嫌かもしれないけど、別に不名誉なことじゃないんだから」 仲間を守ってできた傷だ。誇りに思うことはあっても恥に思うことではない。 「そうだ、寅之助。これは所謂、名誉の負傷という奴だ」 「オマエが言うな」 引き攣った声が手厳しく終夜のことを突っ込む。 その光景にトラの心情を思って苦笑いした。けれどこうした立ち直りの早さが終夜の良いところの一つでもあるのだ。そんなことをふと思ったところで。 ハタ、と。 「そういえば……どういう経緯で出来た傷なのか、あんまり詳しくは聞いてなかったけど」 名誉の負傷と言われ、嫌がるこのトラの態度。単にビショップにやられたのが腹立たしいのだろうと勝手にそう思っていたけれど……。 (そうじゃないのかしら?) 瞳を瞬かせて首を捻る。すると何故か終夜が胸を張ってその口を開いた。 「何を言っておる。先程も言ったであろう。私が転び、寅之助がその巻き添えを食ったのだと」 「え、だからそれは……つまり終夜が転んで、それを助けようとして……でしょ?」 「そなた、少し曲解しておるな。難しく考えず、言葉通り素直に受け止めよ」 「いや、受け止めよって」 むくれるトラをチラリと横目で見る。それから真剣な面持ちでこちらを見つめてくる終夜に視線を戻す。 「……。わからないわ」 早々に白旗をあげたのはもはやこれ以上脱線したくないからだった。時間もわりと勿体無い。夕食の準備だってしなければならない。まだ何にするかも決まっていないのだ。 「そうか。残念だ……。では正解を教えよう」 「いや正解とか言うオマエがそもそも間違ってるだろ!?」 「と、このように、ビショップと遭遇したおり、寅之助はいつものように大層苛立っておった。むしろキレておった。朝にそなたとの睦みあいをみなに邪魔されてしまい、苛々が溜まっていたのであろう。そこで落ち着くがよい、と私は自らの足を一歩踏み出した。今にも殴りあいを始めそうな、そんなふたりの仲裁に入ろうと思うてな。だがしかしそこで悲劇が起きた」 「…………」 「踏み出したは良いが、運悪く足を滑らせてしまったのだ。バランスを崩した私の手は一度宙を掻き、その後なんという偶然か、寅之助の服に引っ掛かったのだ」 「…………」 こめかみに青筋を立て始めるトラを、今一度そっと横目に窺い見る。この辺で話を止めておくべきか否か……真剣に撫子は考え、不安に駆られた。 最後のオチはもはや聞くまでもない。すでにこれだけで充分おおよその予想がついた。その結果も。 (それでむくれてたのね) 助けようとしたのではなく、本当に完全に巻き込まれたのだ。 そして実力の一欠けらさえも発揮できぬまま、結局トラは逃走という手段を取ったのだろう。一度崩れてしまった態勢をもう一度整えるのはなかなか容易なことではない。特にビショップのような気の抜けない相手では、それが命取りになることもある。考えていたら本当によく無事に帰って来られたのだと改めて感心してしまう。 「……というわけで私の巻き添えを食い、ふたり揃って仲良く転んだのだ。背後が傾斜になっておったので、なかなか見事な滑りっぷりであったぞ。しかし寅之助はそれでも声を上げることなく、最後まで勇敢に……」 「テメーのせいで首が絞まって声が出なかっただけだ!」 吼えるようにして訂正事項が入る。相変わらず終夜と接するときのトラはその律儀さが妙に浮き彫りとなる。 「……って、おい、お嬢。お前も笑ってんじゃねぇよ」 「だってトラ」 (むきになって、可愛いんだもの) 言えば確実に拗ねるだろう言葉がすんなりと胸に浮かぶ。開いた口が塞がらないと、つい先程まで 神様の意地悪に目を見張って、唖然としていたのが嘘のようだ。 くすくすと堪えきれない笑いをちいさく零せば、案の定、唇を尖らせたトラが「……覚えてろよ、終夜」ぜってー泣かす。と、実に不穏当なセリフを吐きながら何やら誓いのようなものを立てている。 「そうか…覚えていよう、寅之助」 それに薄く微笑みながら終夜はいつも通り生真面目に応えた。 笑みが零れる。 しあわせなときだった。 とても、しあわせで、だから。 「……撫子?」 「え?」 視界がぼやけていることに、そこで初めて撫子は気が付いた。 「……終夜」 微笑む姿が今にも消えてしまいそうだった。 その儚さに、だから咄嗟に撫子は腕を伸ばした。終夜に触れる為、その存在が今ここに確かにあることを実感する為。 それはそれだけのつもりであったのに、撫子が縋ると終夜は強風にでも煽られたかのようにその足元を頼りなくふらつかせた。 慌ててそれを撫子は支える。 「おお、すまぬな、撫子。最近記憶ばかりか、どうも身体のほうもうまく動かせぬようになってな。そろそろ歩くのも大変に……」 「いつから!? いつからなの、終夜!?」 このことをトラも知っているのだろうか。あまりのことに悲鳴のような声が出た。感情が堰を切って溢れる。悠長に考えている余裕などなかった。 その思いが伝わったように終夜は、ふむ、と一度呟くと、 「こちらの世界に戻ってから……まあ、徐々にだ。寅之助には言っておらぬ。見ている限り、まだ私のことには気付いておらぬはずだ。どうだ、撫子。すごいであろう」 「馬鹿! すごくなんかないわよ!」 そんなこと、ちっともすごくない。 (気付かなかった。トラも、私も、誰も終夜のこと……!) たった一人で、終夜だけがそのすべてを自らの内に抱え込み、微笑んで隠していた。記憶を失う。思い出がなくなる。そんな辛いことを独りで。 怒鳴られたことにややしゅんとなる終夜の暢気さがいっそ恨めしくさえあった。今日この日、この瞬間。撫子が気づき、それを追及するまでおそらく終夜はまだ隠す気でいたのだ。 目に見える不調を誰かに察知されるまで。 誰の目にももはや隠せないところにくるまで。 (終夜はやさしいから) 自分の為に誰の心も掻き乱したくないと考えていたに違いない。彼がそういう人だと、撫子はもうよく知っている。聖職者ではないけれど、それに近いやさしさをもつ人だと。 「戻りましょう。私一人じゃ、いつ支えきれなくなるかわからないから」 (それからすぐ医者に診てもらわないと) 記憶障害がどのような形で終夜の身に害を及ぼしているのか。 わからないが、わからないからこそ、それを早急に診てもらわなければならない。 目に見える傷ならば撫子が診ることも可能だが、殊、この世界の知識についてのもの、というのであれば撫子には出る幕はない。それはこの世界の人間でも難しい原理なのだから。 「馬鹿よ、終夜。こんなの……トラが知ったら悲しむわ」 比較的瓦礫の少ない場所を選んで、唇を噛み締めながら歩を進める。異変に気付けなかった悔しさが胸に滲み、不甲斐無い自分が腹立たしくて仕方なかった。 しかしそうしたさなか、ふいに終夜が足を止めた。 「終夜?」 どうしたのと顔を覗き込む。具合でも悪くなったのだろうかとおそるおそる目を向ければ、そこで初めて終夜が悲しそうな顔をしているのが見えた。さみしいと言った、その言葉に真実添うように。 「……トラが悲しむ、か。そうだな、きっと私は寅之助の悲しむことをしたのであろう。寅之助には何かあれば相談せよと言っておいて、自らはこの体たらくだ。きっと悲しませ、そして怒らせるであろう」 「それは……終夜が心配だからよ」 きっと自分が言わずとも充分わかっているだろうが、それでもつい堪えきれず口を挟む。 「心配だから怒るの。大事だから悲しむのよ」 それは簡単で、とても単純なことだ。けれどそんなシンプルなことを人は時にひどく難解にし、複雑にさせる。 「それは、そなたにも身に覚えのあることか?」 「え?」 ふいにどきりとするような真っすぐな眼差しを向けられ、撫子は困惑した。終夜? と相手の様子をおずおずと窺う。 「あの日、寅之助がそなたを政府から助け出し、組織へと戻ってきた日。長と寅之助……そしてそなたらの三人で話をしたのは知っておる。何を話したか詳しくは知らぬが……あの日以降、そなたも寅之助も何か様子がおかしくなった。当初は有心会から離れたことがその原因かと思うたが、それが理由であるならば寅之助はそもそも離れる決意などしなかったであろう。あやつはそういう男だ。自身が決めたことに躊躇いは持たぬ」 「…………」 その通りだ。その通りすぎて何も言えない。胸が杭を打たれたように痛んだ。 「ならば原因は他にある。これまでになかった原因、今までの寅之助にはなかった……大きな影響を与える、そういったものが」 眼差しは動かない。 どこに逸れることもなく、一心に注がれ。 「……そなただ、撫子」 そう告げることがどこか辛そうにも見えた。 |
|
愛のかたちは不変ではない。 時間に寄り添って、それは移ろう季節のように変わりゆく。 |
|
( ……おしまいにしましょう、トラ ) だから、あの時出来なかったことを、今果たそう――。 |